みなさんは「教養」という言葉を聞いたことがありますか?
教養は、学校の勉強、つまり「知識」とは少し違います。
もちろん、学校で学ぶ国語や数学、社会や理科の知識も大事ですが、教養はそれらを含んだもっと広い意味を持っています。
簡単に言うと、教養は「いろいろなことを知っているだけでなく、それをどう使うかを考えられる力」のことです。
たとえば、ニュースで話されていることを理解できる、他の人の考えを聞いて共感できる、そしてそれを自分の生活にどう役立てるかを考える力が教養です。
今回は、この「教養」の成り立ちから今の時代での価値を考え直し、みなさんにとって教養がどのように役立つのかをお話しします。
はやく結論を教えて!という方は、「教養が今の時代にどう役立つか?」の章から読んでみてくださいね。
いろいろな時代の「教養」って?
教養の歴史を振り返ると、教養の概念は時代や地域ごとに違った形で発展し、多くの社会的・文化的な変化とともに進化してきました。
今を生きる私たちにどのように役立つのかを考えるためにも、まずは、昔の人々が何のために「教養」を身に着けてきたのかを知りましょう!
古代ギリシャと教養

教養のルーツは、古代ギリシャの哲学に見つけることができます。
古代ギリシャでは、「教養(パイデイア)」は個人を徳のある人間に育て、理想的な市民を作り出すための重要な概念とされていました。
この時代の教養は、哲学、倫理、政治、芸術などたくさんの分野の学問にまたがっており、知識と知恵を通じて人間性を深めることが目標とされていました。
ソクラテスやプラトンといった哲学者たちは、教養を通じて「善い生き方」を探求し、人々が正義や徳を持って社会に貢献できるようになることを重視しました。
特に、プラトンの著作『国家』では、理想的な統治者は「哲学王」と呼ばれ、教養を深めた者こそが正しい判断を下し、社会をよりよく導けると考えられていました。
古代ローマ時代の教養
古代ギリシャに続き、古代ローマでも、教養が市民生活や政治において重要視されていました。
ローマの政治家やリーダーたちは、教養があることを国家運営において不可欠と見なしていました。
特に「修辞学(レトリック)」が重要な学問とされ、討論する力や説得力を身につけることが政治や法律の世界での成功につながると考えられていました。
ここからわかる通り、ローマの教育はギリシャの影響を強く受けており、哲学や文学、歴史に関する幅広い知識を蓄えることが理想的な市民像とされました。
彼らにとって教養は、単に知識を増やすことだけでなく、道徳的な判断力を培い、社会に貢献するための準備でもありました。
中世ヨーロッパと教養

中世ヨーロッパにおいても教養は重要視され続けましたが、キリスト教の影響により、宗教的な価値観が教養に大きく影響を与えました。
特に、修道士たちが古代の学問や哲学の書物を保存し、学問の中心となる大学が設立されると、神学や哲学を学ぶことが知識人の必須条件となりました。
しかし、この時代の教養は主に上流階級や聖職者に限られており、一般市民にはあまり広まっていませんでした。
とはいえ、後のルネサンス期に再び古典学や人文学が復興し、より広い層に教養が求められるようになっていきます。
江戸時代の日本における教養
日本に「教養」が広く普及したのは江戸時代です。
この時代、寺子屋という教育機関が一般の庶民に広まりました。
寺子屋では、読み書きや算術だけでなく、礼儀作法や道徳も教えられており、当時の教養は「人としての正しい生き方」を学ぶことと密接に結びついていました。
また、武士階級では「文武両道」という考え方が広まり、武術だけでなく学問や文化にも深い関心を持つことが理想の生き方とされていました。
これにより、武士は政治や外交においても活躍するために広い教養を必要としていたのです。

近代での教養の変化
日本が明治維新を迎えると、西洋の教育制度が取り入れられ、教養のあり方も大きく変わりました。
西洋的な科学技術や思想が導入され、教養は単なる文化的な知識の習得にとどまらず、科学的な思考力や技術力を身につけることも求められるようになりました。
この時代では、「教養」は国際的な視野を持ち、日本の近代化や産業の発展に貢献するための基礎とされたのです。
教養が今の時代にどう役立つか?
このように、「教養」の意味は、その時代を幸福に生き抜くために必要な力に合わせて変化してきました。
では、「現代を幸せに生きるために必要な力」とは何でしょうか?
情報化社会を生き抜こう!
現代は「情報化社会」と呼ばれるように、インターネットを通じて膨大な情報が簡単に手に入る時代です。
Twitter(今はXですが…)やinstagram、TikTokなどのSNSだけでも、たくさんのニュースや人々の生活などの情報が流れてきますよね。
しかし、情報が多すぎると、取捨選択ができなくなり受け身で情報を聞くだけになったり、どれが自分の生活や将来に役立つのか、本当にその情報が正しいのか、どう活用するべきかを判断するのが難しくなりませんか?
ここで必要となるのが、「教養」です。
教養を持つことで、ただ知識を集めるだけでなく、その情報をどのように使えばいいのかを考える力が養われます。
たとえば高校進学について考えるとき、ただ漠然と「なんとなく有名な学校だから」という理由で選ぶのではなく、教養を持っていると、その学校がどのような教育方針を持ち、どんな学問に力を入れているかを調べ、判断する力が養われます。
たとえば、科学や技術に興味があるなら、理系科目が充実している学校を選ぶべきかもしれませんし、国際的なキャリアを目指すなら、語学や国際交流に力を入れている学校が良いかもしれません。

他にも、教養は他の人とのコミュニケーションにも役立ちます。
学校生活や身近な人とのコミュニケーションの中で、「この人とは合わないなぁ」と感じることはありませんか?
学生時代などではそういった人とのコミュニケーションを避けることもできますが、社会に出ると常にそうできるわけではありません。
(もちろん、自分のやりたいことで独力で生きていく道もありますよ)
そういった人と相互理解を深めるためには、幅広い知識と柔軟な思考が必要です。
教養があることで、他者の意見や価値観を尊重しながら自分の考えを伝えることができるようになります。
教養の身につけ方って?
では、どうすれば教養を身につけることができるのでしょうか?
本を読む・オーディオブックを聞く
みなさん、本を読みましょう!
これに関しては言われなくてもわかるかなと思います。
でも、すぐ読めるようになるなら苦労しませんよね。
ここでは、「どうやったら読めるようになるの?」という点について話したいと思います。
- 一日1ページを読むと決める
本を開くと、数百という膨大なページ数…これを数日で読もうとするのは大変ですし、やる気がなくなるのも仕方がないですよね。
そこで、まずは一日1ページを目指してみませんか?
本は図鑑などの絵が多いものでもOK! 読めた日は、昨日より成長できた自分をほめてあげましょう! - 耳で聞く本を活用!
今、世間には「耳で聞く本」があります。
その名も「オーディオブック」! 通学中やお風呂に入るときなど、簡単に聞き流せます。
アマゾンが運営している「Audible」などいろいろな種類があるので、ぜひ利用してみてくださいね。 - 「なぜ?」と思ったことを調べる
「教養をつけること」を目的とすれば、いきなり本を読まなくても、文章を読む時間を作ることが大事です。
日常生活で「これってどうしてだろう?」と感じたことを大切にし、その答えを自分で調べてみる習慣をつけませんか?
例えば、気になったことをまとめたブログを読んでみたり、まとめサイトを見てみるなどの方法があります。
他にもやり方はいろいろあるでしょう。
重要なのは、「目標は高く!でも、初めの一歩は小さく!」です。
一歩目は小さく、一日1ページから始めてみましょう!
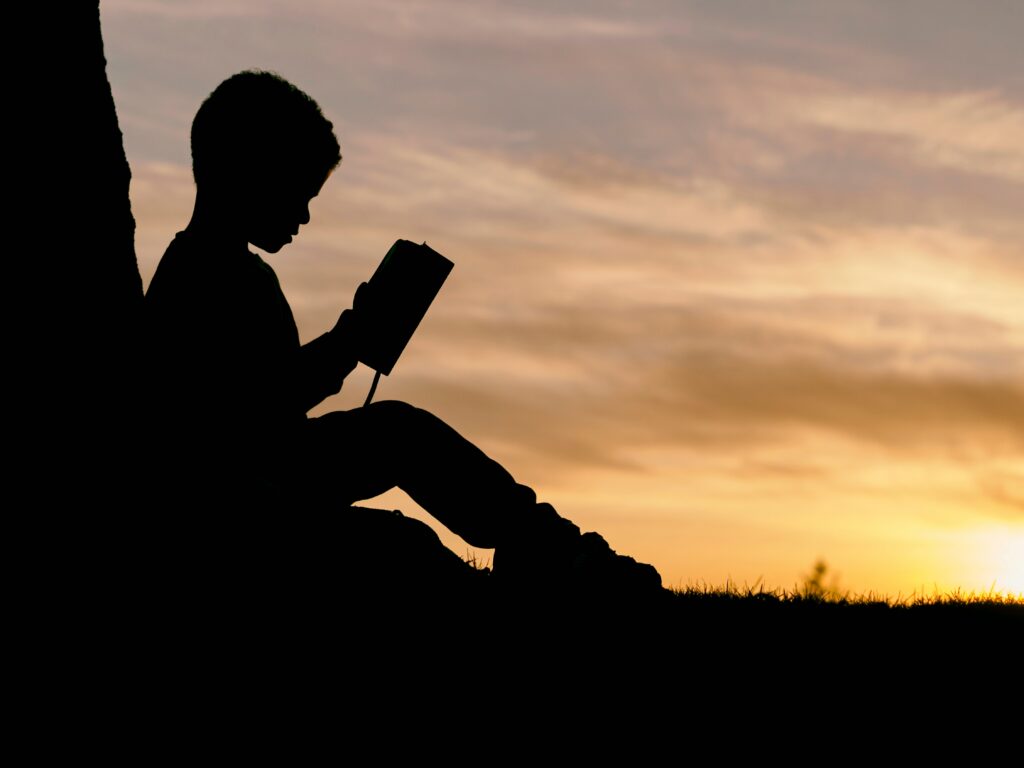
未来に向けた教養の価値
教養は、将来の自分を支える強力な「武器」となります。
社会に出ると、さまざまな問題に直面することがありますが、その解決には多くの知識や経験が必要です。
たとえば、科学者になりたいという方はいますか?
「科学者だから科学の知識があればよい」という考えはとても危険です。
科学は、常に「それがどう使われるのか?」という問いと隣り合わせです。
この判断を間違えると、遺伝子編集やAI技術が、人を傷つける道具になってしまうかもしれません。
歴史や人間社会、社会問題などの科学以外の知識を身に着けることで、あなたの発想や発明がより価値のあるものになっていくでしょう。
どんな時代でも、教養は自分を成長させ、未来を切り拓く力となります。
自分の人生を豊かにするために、たくさんのことに興味を持ち、どんどん学び、自分の未来をもっと素敵にしていきましょう!

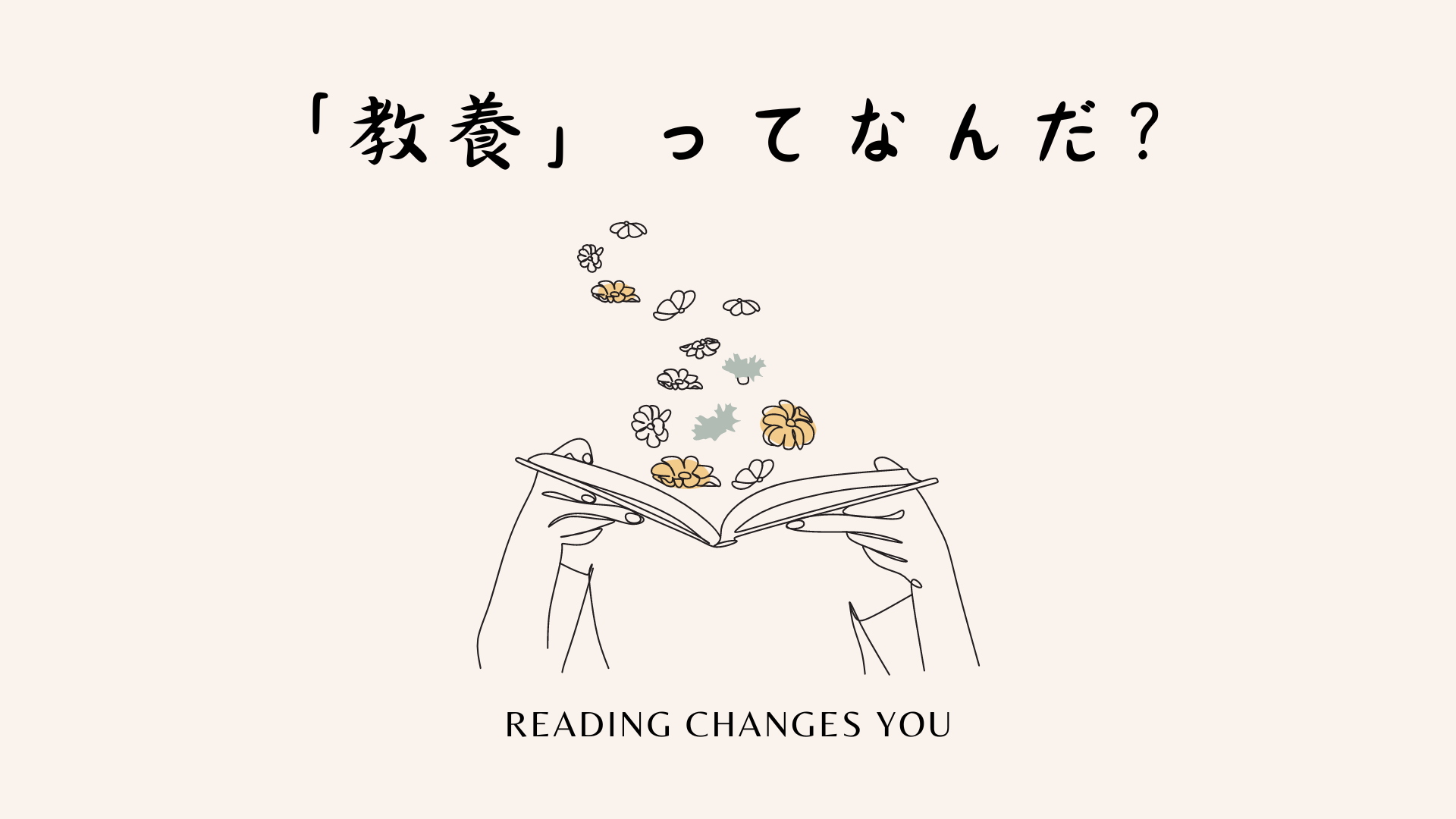







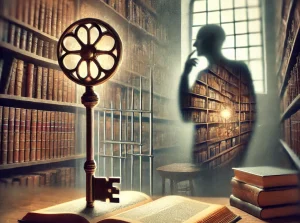
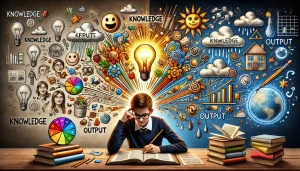
コメント