快晴の空、夕焼け、そして青い海…
身近で何気なく見ているものですが、改めて考えると、なぜ空は青いのでしょうか?
実はこの美しい景色には、共通した理屈があるんです。
この理屈、「レイリー散乱」という名前がついています。
どのような法則かというと、「空気中の小さな粒が光を散らす」というもの。
これだけ聞いてもよくわからないですよね。
これからわかりやすく説明しますので、美しい景色の秘密を探っていきましょう!
そもそも、「光」とは?
「光を散らす」とは言っても、そもそも「光」とは何でしょうか?
一言でいえば、光とは「波」です。(正しくは「波と粒の両方」なのですが、難しい話なのでまたいつか…)
海の波をイメージしてみましょう。
水面に山と谷が交互にできて、それが進んでいきますよね。
光も同じように、目には見えないけれどこの「山と谷」が伝わっていて、それが目に入ると「光」として認識されるわけです。
波と言えば、小さい間隔で山と谷がある波と、大きい間隔で山と谷がある波がありますよね。
実は山と谷の間隔が、「色」を決める重要な性質なのです。

この山と谷の間隔を、波長と言います。
「波長」とは、波が一回ひとつきり揺れる距離です。
海の波を例にイメージしましょう。
一つの波の山から次の山までの距離が波長です。この距離が長い波はゆっくりとした波で、距離が短い波は速く感じられます。
波長と光の飛び散りやすさ
ここまで話してきた「波長」。
これは、「光の飛び散りやすさ」と関連するんです。
「レイリー散乱」という言葉を聞いたことがありますか?
この現象は、イギリスの物理学者であるロード・レイリーによって19世紀の終わりごろに発見されました。
レイリーは、光が空気の中の小さな粒に当たると、その光が散乱されるということに気づきました。
特に、波長が短い光(例えば青い光)は、波長が長い光(例えば赤い光)よりもずっと強く散乱されることを発見しました。
下の図を見てみてください。
波長が短い光の方が、粒に当たりやすい気がしませんか?
その結果、波長が短い光の方が散乱しやすいのです。
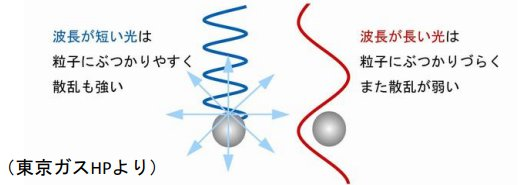
では、この散乱が空の色とどう関係あるのでしょうか?
空の色の真相
空から降り注ぐ太陽光は、様々な色(波長)を含んでいます。
この太陽光と空の色の関係に迫っていきましょう。
空はなんで青い?
「レイリー散乱」の説明、青い光は他の色よりも小さな粒によってより散乱されるため、青い光は他の色に比べてより幅広く空全体に飛び散ります。
すると、青い光が空のあらゆる方向から目に入るようになります。
その結果、青い光はいろいろな角度から目に入り、晴れた日では空が青く見えるのです。
夕方の空はなぜオレンジ色?
昼間、空が青い理由がわかりましたね。
では、夕焼け空が赤くなる理由はなんでしょう。
それは、夕方は昼に比べて、光が届く経路の長さが変わることが影響しています。
昼間の光に比べて、夕日は斜めに大気の中を通って届きます。
この長い経路の中で、散乱しやすい青い光はあちこちへ飛び散ってしまい、私たちの目に入る頃にはほとんど失われてしまいます。
その結果、残った波長の長い赤い光が届くため、夕日は赤く見えるのです。
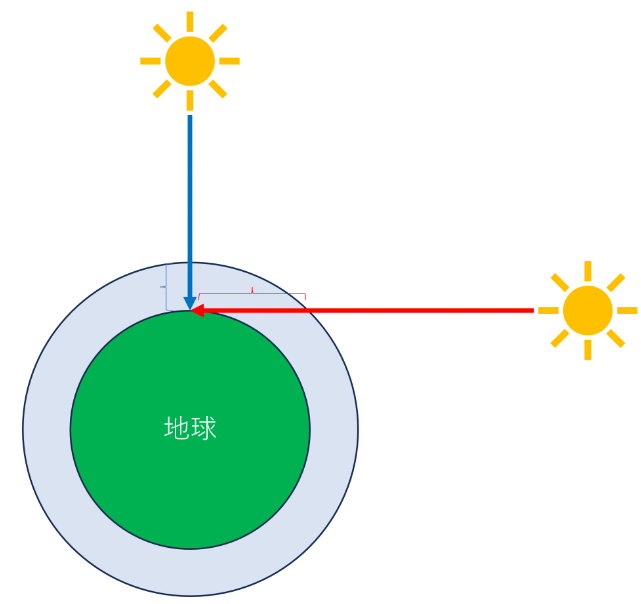
まとめ
今回は、空の色と光の反射の関係探ってみました。
「光」が「小さな粒に当たると散乱する」という性質を持つことにより、空が青く見えるということがわかりました。
明日は空に目を向けて、観察してみましょう!
身近だけど不思議な現象は、勉強している知識で説明できるものがほとんどです。
ぜひ知識を活かして、身の回りの不思議を解明していきましょう。
※太陽を直接見ないように気をつけましょう。









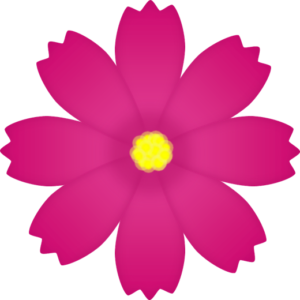

コメント