幽霊、占い、未確認生物…
もはやエンタメ化すらしているオカルトは、真夏の心霊番組や動画サイトで、これでもかというほど流れてきます。
オカルトとは、科学では説明できない不思議な現象や出来事のことを言います。
心霊番組をつい見てしまう。お化け屋敷で怖いけど楽しいと感じたり、占いを信じたくなる。
そんな気持ちを抱いたとき、私たちはオカルトに少し引き寄せられているのかもしれません。
でも、どうしてこんな不思議なものに人は惹かれるのでしょうか?
オカルトの始まり
オカルトの始まりは古代。
古代エジプトや古代ギリシャでは、占星術や霊的な儀式によって、自然災害や政治などの判断が行われていました。
また、日本の平安時代には、鬼や妖怪といった超自然的な存在が人々を脅かしていたと言われ、陰陽師の「安倍晴明」が酒呑童子という鬼を討伐した話もありますよね。
この酒呑童子、「赤疱瘡(あかもがさ)」という疫病だとか、海の向こうから来た盗賊だとか、いろいろな説があります。

さて、これらの事例にはある共通点があります。
それは、理解できない現象を、オカルト的な存在や儀式によって制御しようとしているということです。
自然災害、疫病のいずれも、科学が発展していない時代では理解できない脅威でしょう。
昔のオカルトは、人々の生活に深く根付いており、自然や社会を理解するための手段として利用されていたのです。
さて、現代では科学技術が発展し、自然現象もほとんどが科学で説明できるようになりました。
それでもオカルトが現代でも信じられているのは、なぜでしょうか?
昭和のオカルトブームと現代のオカルト
オカルトは昔の話だけではありません。
昭和時代の日本では「オカルトブーム」と呼ばれる現象が起き、多くの人が超常現象やUFO、怪奇現象に興味を持つようになりました。
雑誌やテレビ番組では、心霊現象や超能力の話題が取り上げられ、たくさんの人が楽しんでいました。
最近でも、インターネットやSNSの影響で「陰謀論」など、オカルト的な話題がさらに広がっています。
UFO目撃談や、都市伝説のようなものがSNSで話題になることも珍しくありません。
オカルトは、科学技術が発展した現代でも依然として人気があり、人々の心をつかんでいます。
人がオカルトに魅力を感じる理由を、いくつかの観点から考えていきましょう。

心理学の視点:なぜ人はオカルトを信じ続けるのか?
まずは、心理学の観点から見てみましょう。
人間は未知のものに出会ったとき、二つの感情を抱きます。
それは、「好奇心」と「恐怖心」です。
そして、好奇心や恐怖心を感じると、それを理解しようとする習性があります。
何かが「説明できない」「よくわからない」と感じる時、それを説明できる理由を(こじつけでも)みつけてスッキリしたいと思うのです。
人は理解できないことを嫌い、それを何とか説明するために、超自然的なものやオカルトを信じることがあるということですね。
人は、「理解できないこと」に出会ったとき、その理由を見つけるためにオカルトに行き着くことがある。
社会学の視点:社会の不安とオカルトの安心感
社会学的な視点では、オカルトや超常現象に対する関心が、集団心理や社会の不安と関係しているといわれています。
社会が不安定な時期や、変革の時期には、オカルトやスピリチュアルなものへの関心が高まることがよく見られます。
例えば、経済不況や戦争、パンデミックといった状況では、人々は自分たちの将来が不透明で、不安を感じやすくなります。
このような時期には、オカルト的な現象やスピリチュアルな教えが、漠然とした不安感に理由を与え、「安心感」や「意味」を提供するため、人々がそこに引き寄せられることがあるのです。

集団心理もオカルトへの関心を高める要因です。
ある社会やコミュニティの中で超常現象が信じられている場合、人々はその信念に合わせようとするのです。
これが「社会的証明(Social Proof)」という心理で、他者が信じていることに従うことで、安心感や一体感を得ようとします。
オカルト的な話題が流行すると、それに乗っかる形で信じる人が増えるのもこのためです。
① 人は、社会の先行きがわからなくなると、オカルトに縋ることがある。
② 他の人と同じことを信じていることで、安心感を得ようとする性質が、オカルトを魅力的にしている。
まとめ:オカルトは人類が人類たる証拠
オカルトの魅力は、歴史や文化、心理に深く根付いており、私たちが抱く「不思議」「怖い」「知りたい」といった気持ちに応えるものです。
科学技術が進んだ現代でも、オカルトが完全になくならない理由は、こうした人間の本能的な欲求にあるのですね。
時代とともに形を変えながら続いているオカルトは、人類が人類たる証拠の一つといえるのかもしれません。








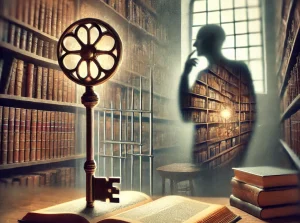
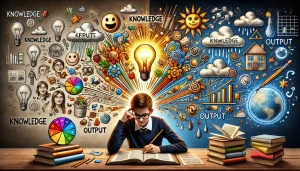
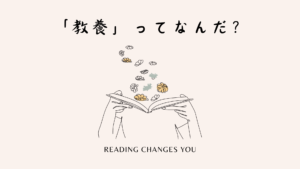
コメント